戦後、焼け跡でぶらついていた渥美清に声をかけたのは浅草のフランス座関係の人間だった。
「お前さん、いつまでもヨタってばかりしていたら、いずれブタ箱行きという事にもなりかねないよ。どうだい、一つ、この辺で足ィ洗って、オレの一座で幕引きをやってみる気はねえか」
こうしてフランス座での役者稼業が始まる。
![]()
彼の一人芝居に、こんなのがあった“渥美清”堀切直人 晶文社より
帽子をかぶり、サングラスをかけ、コーンパイプをくわえ、マッカーサーに扮して舞台に現われ、でっち上げの英語を勝手にまくしたてる。ついで、台湾総統の蒋介石に化けて、でたらめの中国語をしゃべり、時折、それにチャーシューメンといった言葉を交えた。さらに、ソ連の書記長スターリンになってロシア語らしきものを、フランスの軍人ドゴールとなってフランス語らしきものをしゃべる。そうかと思うと、突然、ターザンに変身して、アーッアッアッアッと叫び、チンパンジーのチータと化し、ウォホッウォホッと舞台を駆け回る。物真似が達者で、インチキ外国語が楽しく、次に何が出てくるのか予想できない面白さに満ちていた。
渥美清は客を笑わせるだけでなく、客に涙を流させもした。頭に一円玉台のハゲがある、ちょっとオツムの弱い若者の役は絶品だった。「床屋のバカ倅が、おとうとの恋人に恋してしまい、なかなか告白できずにいる役をやった時などは踊子さんたちが舞台の袖に集まって、渥美やんの一挙手一投足を見つめていた。最初はお腹を抱えて笑っていた踊子たちも、芝居が佳境に入るとハンカチを握り締め、目を真っ赤に泣きはらしていた。
そして、この頃に“男はつらいよ”のリリーを思い起こさせる過去があった。
渥美清とM・K子との関係はフランス座時代も続いていた。M・K子は川崎セントラルからフランス座に移り、踊子として舞台に出ていた。当時フランス座の経営者となった松倉久幸は「歌った、踊った、喋った、泣いた、笑われた」でその頃の二人のことをこう語っている。「M・K子というその踊子は、踊りもうまくきれいな子でしたねえ。気立ても優しく、本気で渥美に惚れ込んでました。その頃の渥美はバクチ好きの大酒呑みという、芸人の典型でしたから、K子もずいぶん苦労したでしょうが、渥美のほうもこの子にはほれていたと思いますよ。キャバレーで自分のショクナイ(内職)がないときでも、K子が出番を終えるのを楽屋口でじっと待っていたりしてましたからね」。





















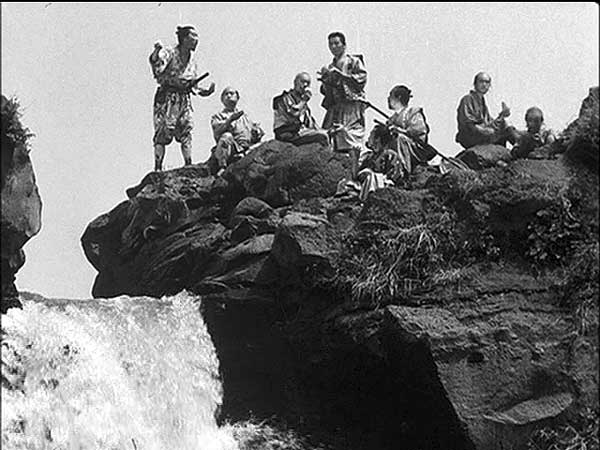





 。
。 フジテレビ“男はつらいよ”
フジテレビ“男はつらいよ” 昭和43年10月から翌年3月まで放送
昭和43年10月から翌年3月まで放送 奄美大島で、寅はハブに噛まれて死ぬ。
奄美大島で、寅はハブに噛まれて死ぬ。

 ユマニテク専門学校様のマジパン体験コーナー
ユマニテク専門学校様のマジパン体験コーナー

 青山里会様のブース
青山里会様のブース



























